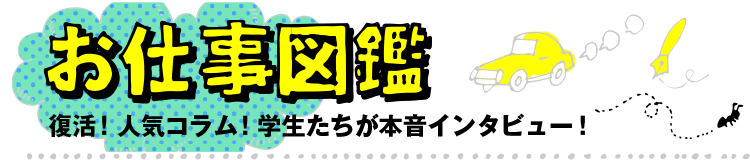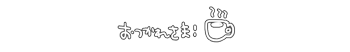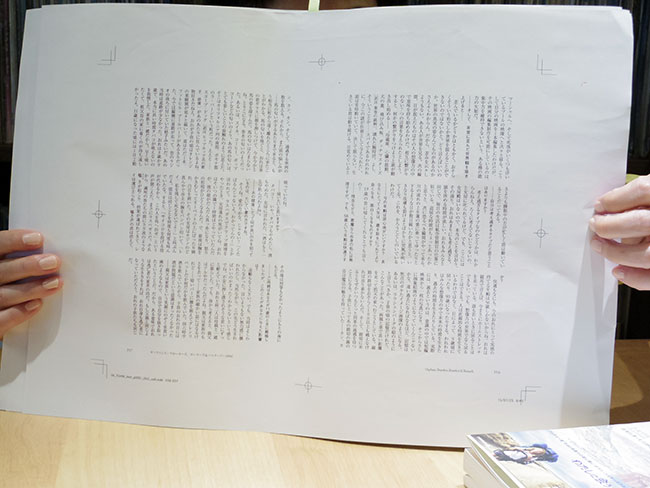13,14歳の時にはすでに翻訳家になろうと思っていた
まず、翻訳家になろうと思ったきっかけを教えてください
子供のころから本が友達。とくに小説が好きでした。
小学生のころはずっと図書館にいるような内向的な子供で、家に帰ってきてからも本。親に怒られるくらい本を読んでいました。
中学生になってからは、レコードやFEN(米軍放送ラジオ)を通して洋楽を聴くようになりました。でも何を言っているの分からない...。それでレコードに付いている英文の歌詞カードを自分で訳し始めたんです。辞書を使って単語や文法を1つずつ調べていくのがすごく楽しかったんです。だから13,14歳の時には漠然とではありますが、すでに翻訳という仕事がやりたいと思っていました。
高校時代には1年間休学してアメリカに留学しました。
その後日本に帰ってきて受験をして早稲田大学に入学、アメリカ文学やイギリス文学に興味があったので英文学を専攻しました。
大学でも、1年間は交換留学生としてアメリカ・オハイオ州の大学で過ごしました。
大学卒業後は就職した出版社を1年弱で辞め、派遣の仕事をしながら翻訳学校に通い、チャンスを探りました。
残念ながら閉校してしまいましたが、私の通ったユニ・カレッジは少人数制で、現役の先生方が丁寧に指導し、ときには下訳などの仕事もくださる素晴らしい学びの場でした。

来るもの拒まずという感じです(笑)
ジャンルはバラバラですが興味をひかれる作品、自分でできると思うものをお引き受けしています。読む本は子どもの頃からきわめて“雑食”です。
翻訳は一人ではなく、共同でもやります!
あります。大抵は一人でやりますが、リリースまで時間がない、ボリュームのある作品なので手分けしようなど…いろいろな理由で共同作業になることも。
短編集などは4,5人で作業をすることもあります
まずは文体を決めていきます。
たとえば『わたしに会うまでの1600キロ』は回想録で、さらさらと読んでいける文体でした。であれば、なるべく平易な言葉で淡々と読み進められる日記風の語り口にしよう、と共訳者と話し合って決めました。
あとは表記ですね。ここは漢字、ここはひらがなにするとか、しないとか。自分たちの中でルールを決めて訳していきます。また登場人物の一人称も決めておきます。この人は「僕」、この人は「俺」、この人は「私」という感じです。
原稿ができたら共著者と互いの原稿を読み合い、感想を出し合いながら詰めていきます。それぞれ得意分野があるので、互いの間違いなどを指摘しながら最終に持っていきます。提出した原稿は編集者が何度もチェックしますが、そのときに頂く意見はものすごくありがたいです。多くの場合、編集者は一番最初の読者ですから。
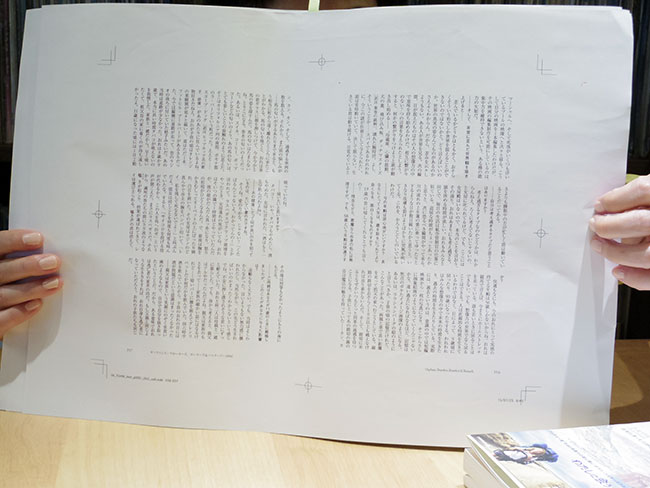
『わたしに会うまでの1600キロ』のこと
『わたしに会うまでの1600キロ』だったら3,4日くらいですかね...
ええ!? 英語の本なのに日本語の本を読むのと同じようなスピードじゃないですか!
急いで読めばそのくらいです。でも読めないものは読めないですよ。日本語で読んで難しいものは英語でも難しいということです(笑)。
この作品の作者は私と同い年で、アメリカの大学での専攻も英米文学と女性学で私と一緒だったんです。だから親近感がありましたし、ぐいぐい引き込まれました。
今、ベストセラーになっていますよね、映画にもなりましたよね?
はい。ベストセラーとまでは言えないけれど、アウトドアが好きな方にも読んで頂けているようでうれしいです。映画も骨太で、とても見応えがありました。機会があったらぜひ観てください。